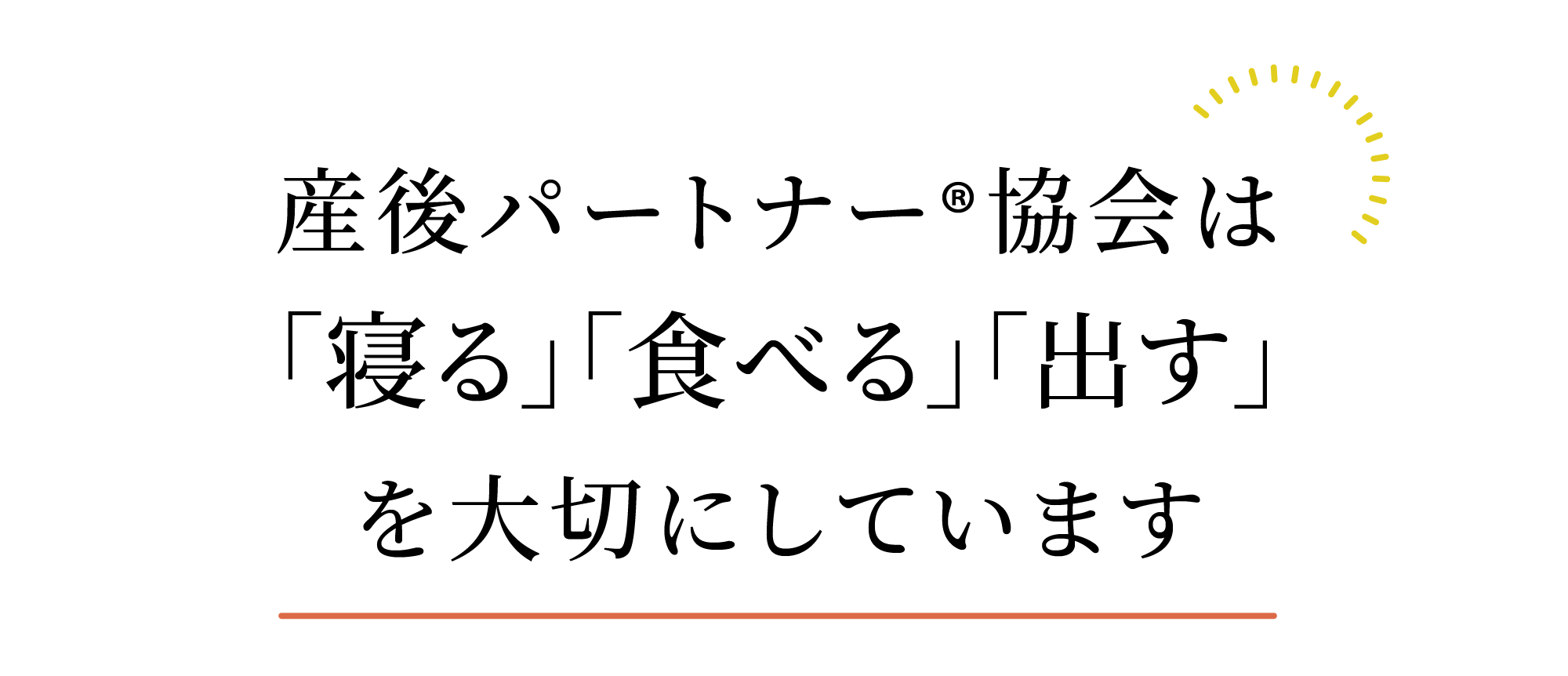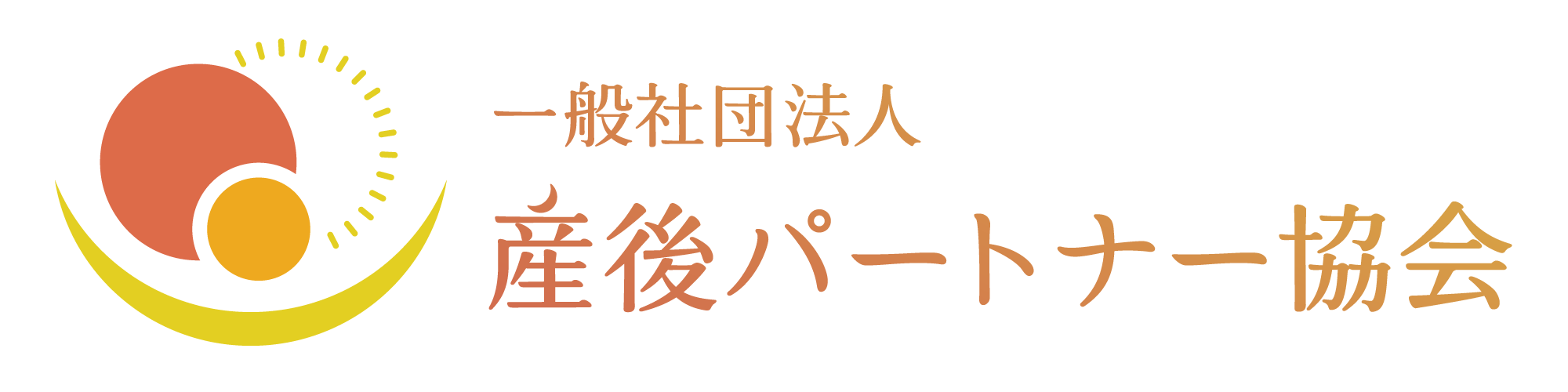産後パートナーは、産前産後の
ママの日常に寄り添う身近な存在。
産後はいつもの日常が一変します。
今までは好きな時間に食事をして、夜になれば十分な睡眠をとれていたのに・・・赤ちゃんのお世話が始まるとゆっくり食事をしたり満足に眠れなくなってしまいます。
その結果、心身にゆとりがなくなり育児を楽しめなくなってしまうことも。
産後パートナーはママの「寝る・食べる・出す』という人生において不可欠な部分を支えてママの心と身体に余裕をつくります。
産後であっても最大限、今までと同じ暮らしができるように。
産後パートナーは産前産後のママの日常に寄り添い支える存在です。


産後パートナーは、産前産後のママのご自宅へ訪問し、
ママが必要とする支援を提供いたします。
産後パートナーは、産前産後のママのご自宅へ訪問し、ママが必要とする支援を提供いたします。
例えば・・・

赤ちゃんのお世話

きょうだいのお世話

料理

掃除・片付け

気持ちの吐き出し

お出かけ同伴

買い物代行

育児や社会資源の情報提供

赤ちゃんのお世話

きょうだいのお世話

料理

掃除・片付け

気持ちの吐き出し

お出かけ同伴

買い物代行

育児や社会資源の情報提供

産後は身体が未回復にも関わらず、赤ちゃんとの生活が始まります。しかも産後はホルモンバランスが乱れるため、精神が不安定になりやすい状況。
このような状態で、赤ちゃんのこと、家のこと、自分のことを全て充実させていくのは難しくて当然です。
昔は「床上げ21日」と言われるように、産後3週間は休養し、周囲の人々がママをサポートする文化がありました。しかし現代では核家族化が進み、身近にサポートしてくれる人がいない家庭が増えています。パートナーも仕事で不在がちであったり、親も遠方に住んでいたり、自身の仕事を持っていたりして、十分なサポートが得られないケースが少なくありません。

出産後の女性の体は大きな変化を経験し、回復には時間がかかります。この時期に適切なケアを受けられないと、産後うつや育児ノイローゼのリスクが高まり、母子の健全な関係構築にも影響を及ぼす可能性が出てくるでしょう。
産後パートナーは、このような現代社会の課題に応えるために生まれた、ママとその家族の日常生活をサポートする専門家。
基本的な生理的ニーズである「寝る・食べる・出す」を支えることで、ママが心身の回復に集中し、赤ちゃんとの時間を穏やかに過ごせるよう手助けします。

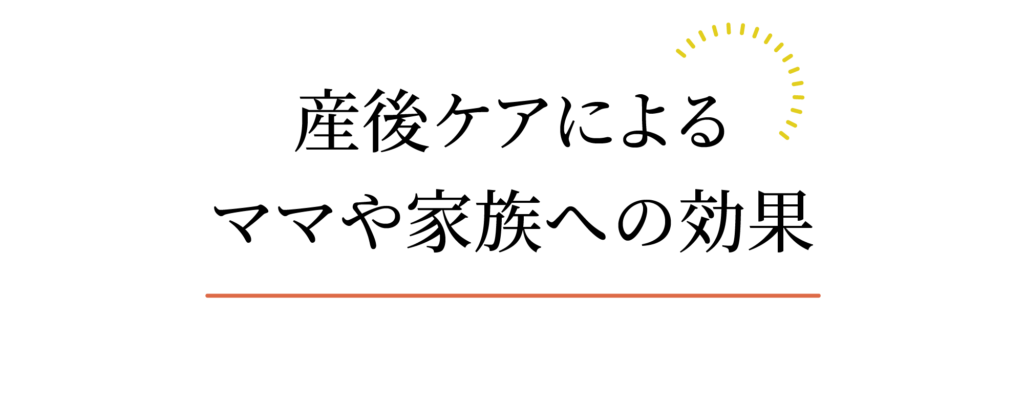
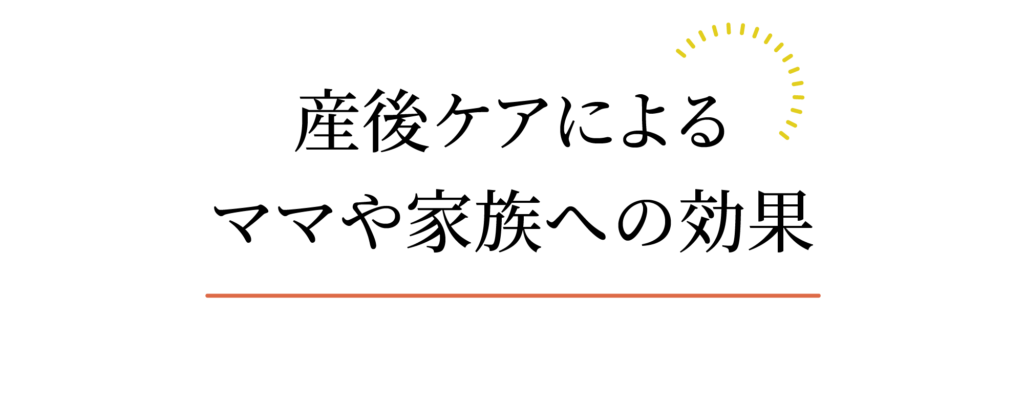
産後の身体回復期にあるママ
- 出産による損傷、疲労、痛み、ホルモンバランスの変化があり、普段と同じようには生活ができない状況。
- 頼れる人がいない場合、心身が十分回復していないまま、赤ちゃんのお世話だけでなく家事・きょうだいの育児が重なる。
- 産後に十分な休息が得られないと、不調が長引く。
産後パートナーが家事と育児を行うことで、ママは適切な休息がとれるため身体の回復が進みます。

睡眠不足に悩むママ
- 夜間の授乳やミルク、赤ちゃんのお世話による睡眠不足・慢性的な疲労感がある。
- 日中も赤ちゃんのペースに合わせる必要があり、休息の時間が確保できない。
産後パートナーが赤ちゃんを見守る間にまとまった睡眠や休息がとれ、心身の疲労が軽くなります。また、判断力や感情のコントロールが改善し、赤ちゃんと穏やかに向き合えるようになります。

食事の準備や栄養摂取が難しいママ
- 赤ちゃんから目が離せないことで、簡単なものだけを不規則に食べている。
- 授乳中は自身の栄養状態に不安がある。
産後パートナーが家にあるものを使い、ママの状態に合わせた食事を作ります。栄養バランスの良い食事が定期的に摂れるようになり、ママの体力が回復します。 特に授乳中のママは必要な栄養素を摂取できることで、母乳の質や量にも好影響につながる可能性があるでしょう。

家事の負担に悩むママ
- 洗濯物が溜まり、部屋は散らかったまま。
- 日常的な家事が後回しになることでストレスが増加する。
産後パートナーが基本的な家事を行い、清潔で快適な環境で過ごせるようになります。 物理的な環境が整うことで、ママや家族の精神的な余裕も生まれます。

核家族で孤立しがちなママ
- 身近に頼れる家族がおらず、育児の悩みを相談できる相手がいない。
- 孤独感や不安感が強く、育児に自信が持てない。
信頼できる産後パートナーとの対話を通じて孤独感が減るでしょう。 育児の悩みを聞いてもらい、今必要なことを教えてもらうことで安心感が生まれます。

産後の心理的不安を抱えるママ
- ホルモンバランスの変化や育児ストレスから不安や気分の落ち込みがある。
- 産後うつの初期症状が現れているかもしれないと感じつつも、頼り先が分からない。
産後パートナーのサポートにより「寝る・食べる・出す」という基本的な生活ニーズが満たされることで精神的な安定を取り戻します。 必要に応じて産後パートナーから専門家へつなぐことで、早期に対応ができる可能性が高まります。

上の子とのバランスに悩むママ
- 赤ちゃんのお世話に追われ、上の子に十分な時間や注意を向けられないことに罪悪感を感じている。
- 上の子の退行行動(赤ちゃん返り)などに対応する余裕がない。
- 切迫早産などの寝たきり状態で、産前の家事・上の子の育児がままならない。
産後パートナーのサポートにより、上の子との質の高い時間を確保できます。 上の子はママと濃い時間を過ごすことで精神が安定し、家族全体のバランスが取れ、きょうだい関係の構築もスムーズになるでしょう。

仕事復帰を控えたママ
- 育休終了後の生活リズムの構築や保育園準備に不安を感じている。
- 産後の体調管理と仕事の両立に不安がある。
産後パートナーが「寝る・食べる・出す」をサポートすることで生活リズムが整い、復職への心理的・物理的準備がスムーズに進みます。 育児と仕事の両立への見通しが立ち、自信を持って復職できるでしょう。